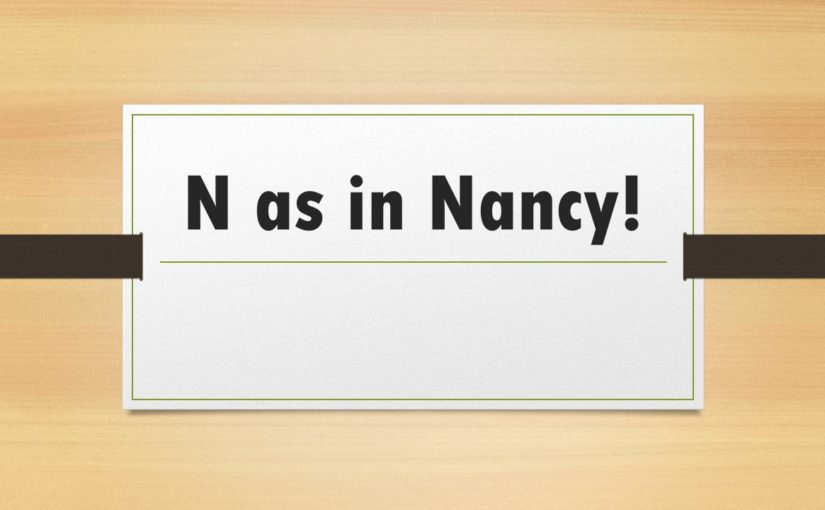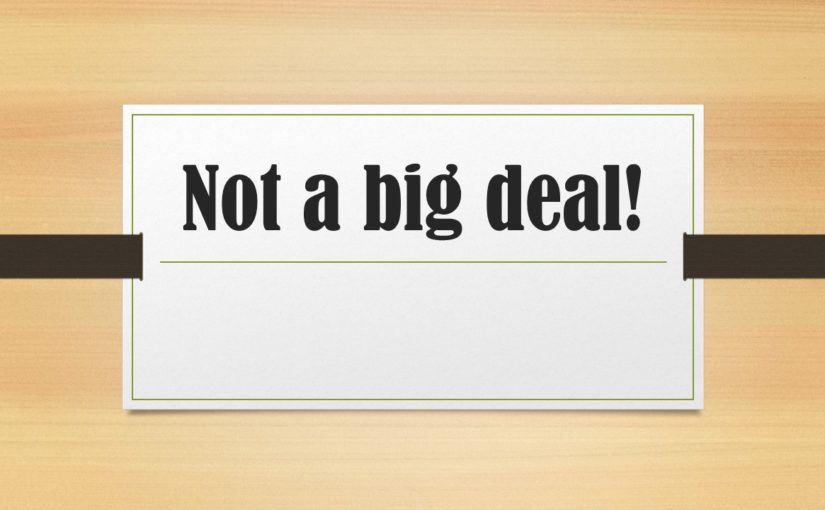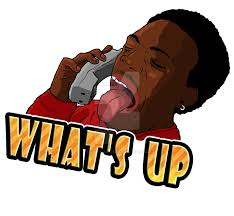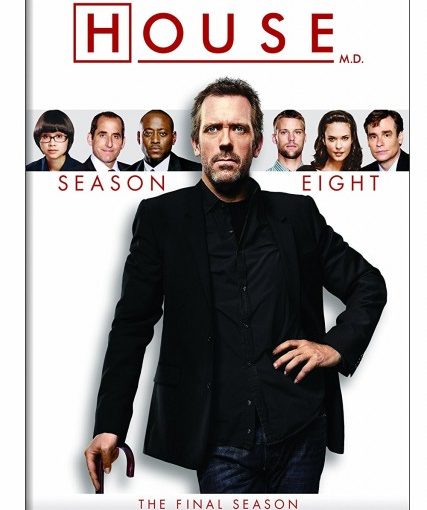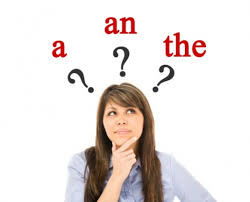関西のお笑い芸人がよく使うフレーズに「なんでやねん!」がありますね。今回は、この表現を英語でどのように表現するのかと取り上げたいと思います。
「なんでやねん!」は関西弁ですから、標準語で言うと「なぜですか?」でしょうか。そうすると、”Why?”という表現が浮かんできますね。これでも構わないと思いますが、私がアメリカに留学した時には違う表現を知りました。
私が留学した大学の医療系学部(Health Professional Division)は、医学部(Osteopathic Medicine (D.O.))、歯学部(Dental Medicine (D.M.D.))、薬学部(Pharmacy (Pharm.D.))、検眼学部(Optometry (O.D.))、看護学部(Nursing (Entry-Level))などから成っています。同じ校舎を学部横断的に使っていますので、医療系学部の学生同士の交流がさかんです。これらの学部の中で、検眼学部(Optometry (O.D.))に在籍していて、日本語がとても流ちょうなアメリカ人と友達になりました。彼は日本を訪れたことも住んだこともないにもかかわらず、本当に日本語が流ちょうでした。どのようにその語学力を身に付けたのかと聞くと、日本のドラマをたくさん見て学んだというのです。彼と知り合って思ったのは、外国語を身に付けることは自国にいてもできるのだということでした。彼は、「アケオメ、コトヨロ」も知っていました(笑)。
ある日、彼が「なんでやねん!」といったのです。アメリカでアメリカ人の口から関西弁を聞くとは思わなかった私は、「それ、英語でなんていうの?」とすかさず聞き返しました。
“What the heck!”
初めて知る表現でした。
ちなみにいくつかの辞書でどのように表現されているか調べました。
ジーニアス英和大辞典「なんてこった」
リーダーズ英和辞典「どうだっていうのだ、かまわないじゃないか」
ロングマン英英辞典 “used to say that you will do something even though you really should not do it”
どこにも「なんでやねん!」の訳語はあてていません。しかし、ネイティブ的な感覚としてはこの表現がしっくりくるのだと思います。
“What the heck!”
皆さんも使ってみてくださいね。