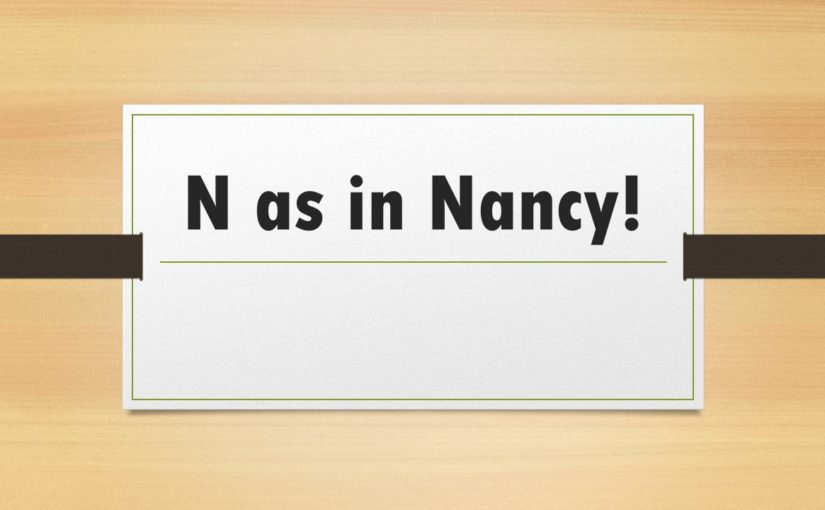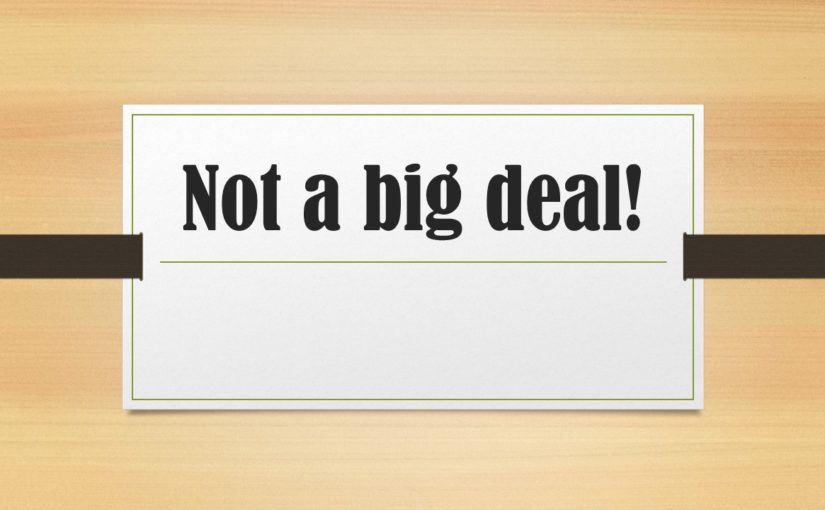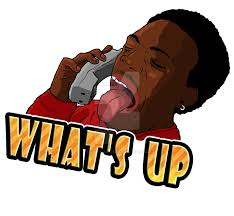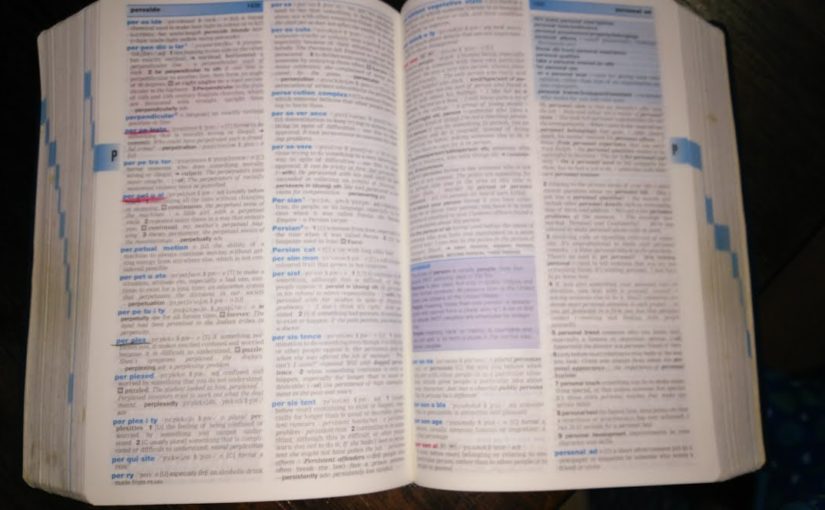留学中は、すべての講義をボイスレコーダーで録音して、講義が終わった後に、図書館や自宅で再度その録音を聞きながら、復習をしていました。ハンドアウトと照らし合わせながら、録音された講義を注意深く聞くのですが、いまいち聞き取れない言葉があるときは、再生速度をゆっくりにして、どのように発音されているかを聞き取るようにして対応していました。それを繰り返していたある日、聞き取れるけれど意味が分からない英語表現にぶつかりました。
“It’s up to you.”
講義中は、何名かの教員の口からこの言葉を聞きました。普通の速度で発音されても聞き取れるけれど、意味が分からない。日本人のクラスメートに助けを求めました。すると、
「あなた次第だよ!」
ということでした。なるほど!!!合点がいくようになりました。
ロングマンの英英辞典では次のように説明されています。
“be up to somebody” = used to say someone can decide about something: You can pay weekly or monthly – It’s up to you.
「決定権は”You”にありますよ。」ということですね。身をもって体感したフレーズでした。
“It’s up to you.”「あなた次第だよ。」
この表現の意味を知ってから、自分の考えをしっかり持とうという意識が強くなりました。自分がどうしたいか?どう生きたいか?留学経験をどのように活かしたいのか?
だれもが経験できるわけではない留学をした私にとって、留学で学んで体得した知識や技能を、自分だけの経験に終わらせたくないというのが自分の考えでした。いろんな方に支えられて留学できたわけなので、恩返しを含めて留学経験をいろんな人とシェアしたい。これが私の帰国後の大きな目標になりました。
帰国して医療機関に勤めているときは、留学経験で学んで体得したものを職員教育に活かしました。また、実習にくる学生に対しても、留学で学んで体得したものを教育に活かしました。現在は大学で教鞭をとっていますが、いろんなことが学生教育に活かせています。私が在籍する大学と、私が留学した大学との間の海外実習の提携、アメリカの大学教育ですでに行われているアクティブ・ラーニングの本学での導入。
“It’s up to you.”
いろんなことに気づかせてくれた英語表現でした。