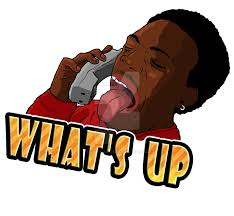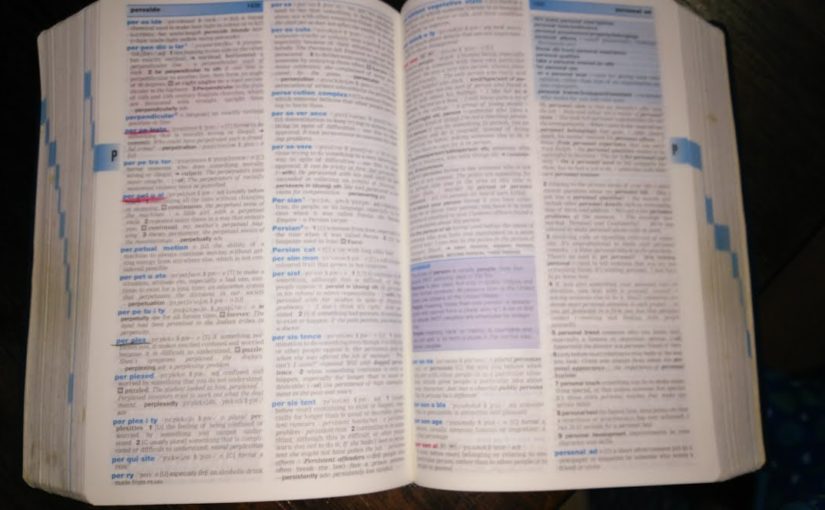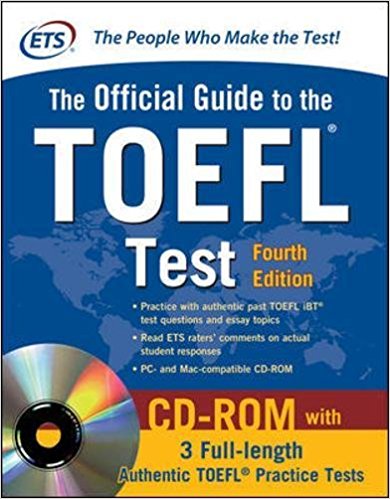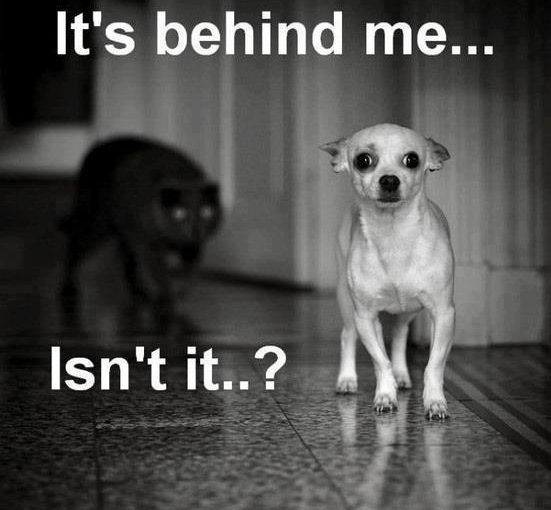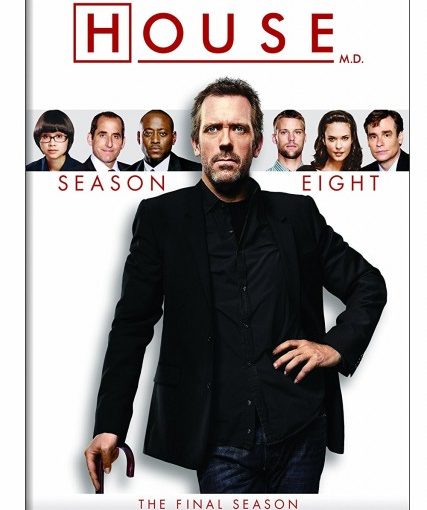私は英語の4スキルの中で、listeningが一番弱いと自覚しています。日本でTOEFL iBTの勉強をしている時に、いかにlistening力をつけるにはどうすればよいか色々調べては試しました。
一時期は、英語のCDを片方のイヤフォンで片耳で聞く方法を実践しました。片耳しか音が聞こえないので意外と集中して聞くようになりました。
もう一つの方法は”Shadowing”です。動詞は”Shadow”ですね。ロングマンの英英辞典では以下のように説明されています。
Shadow = to follow someone closely in order to watch what they are doing
Listeningに関してShadowするとは、話されている英語のスピードについていきながら、聞こえた英語を発音していくことです。
例えば、テレビのニュースを聞いて、アナウンサーの話す内容を日本語で発音してついていくことはできるかと思います。これを英語についてやってみるのです。最初はうまくついていけなかったりすると思いますが、続けてみることです。1日5分と決めたら、毎日5分間Shadowingを続けるのです。
もし、TOEFL iBTのCDを持ち合わせているのであれば、そのCDを聞いて、聞こえた英語についていきながらすぐさま口にすることです。
もし、NHKのラジオ英会話を毎日聞いて勉強されているのであれば、インストラクターの指示を聞きながらでも結構なので、インストラクターが話している英語の文章についていって発音してみることです。
もし、CNNやABCなどのアメリカのニュース番組を見る機会があれば、アナウンサーの話している英語についていきながら発音してみることです。
「ローマは1日にしてならず」といいます。巨大なローマ帝国も小さな一歩から始まったはずです。偉大な野球選手として今も活躍しているイチロー選手も、「小さいことの積み重ねがとてつもないところにたどり着く方法である。」と言っています。Shadowingも、まず1分やってみて、次の日は1.5分やってみる。小さな努力の積み重ねが、Listening力の向上にとどまらず、自然な英語表現の修得、アクセントの修得など、英語力が自然と向上していることに気が付くでしょう。
「継続は力なり」です。私も仕事をしながら、家族が寝静まった夜の11時からの2時間をTOEFL iBTの勉強にあてて毎日続け、2年の末に留学を手にしました。