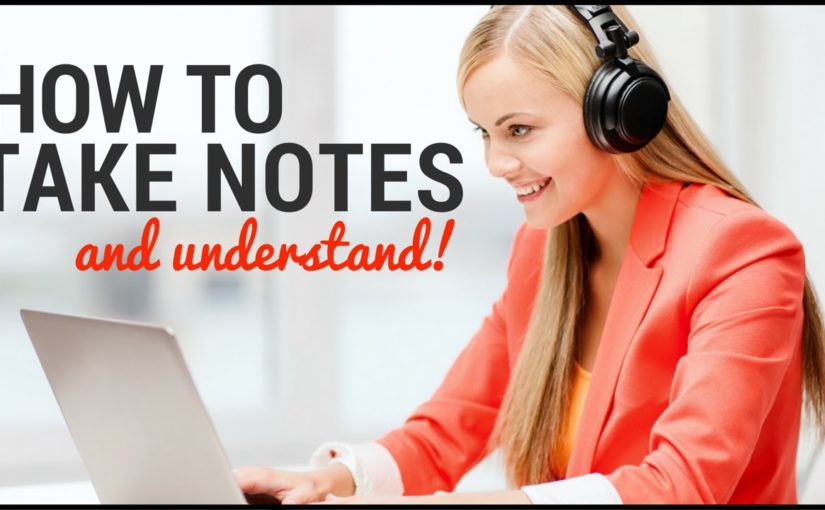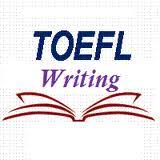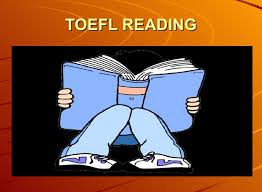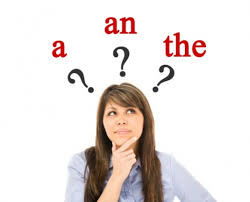今回はSpeakingのスキルについてです。TOEFL iBTの大きな特徴は、このSpeakingのスキルを客観的に評価する点です。Speaking以外のスキルであるReading, Writing, Listeningは自主学習で何とかなるスキルですが、Speakingのスキルは、自己流で話しても、それが正しい話し方(答え方)なのかが評価できません。よって、自主学習によるスコアの上昇は難しいと実際感じました。
地元の英会話スクールに通いました。そこのインストラクターは、全員英語を教える免許を持っているアメリカ人とイギリス人でしたので、学ぶ内容はとても良かったのですが、TOEFL iBTのSpeakingのスコアを短期間で上げたいと思うと、彼らはTOEFL iBTを受けたことがないので、あまり要領を得ませんでした。
そこで考えたのが、TOEFLに特化した学校に通うことでした。私の地元には残念ながらそのような学校はありませんでした。調べたところ、東京にはいくつかあることがわかりました。週末にTOEFL iBTのSpeakingのコースを提供している学校をいくつかリストアップし、模擬授業を受けに2~3回上京しました。その結果、私の地元からも通いやすい秋葉原にある学校に決めました。コースの期間は約3カ月弱。毎週日曜日の午前中に新幹線に乗り、英語のCDを聞きながら上京しました。90分のレッスンを受講後、帰りの新幹線の中でも英語のCDを聞きながら帰るということを繰り返しました。平日は、仕事を終えて帰宅後、家族が寝静まった夜にSpeakingの課題を練習して、日曜日のレッスンに臨みました。
そのSpeakingのコースは20点(30点満点)を目標にした内容でした。日本にいながらの勉強では、20点までしかスコアを上げられないものなのかと当時は思いました。結果、私の最高点は19点でした。コースを受講した当初は、なかなか英語が口に出なくて苦労しましたが、3か月後には19点をとれるまでになれたので、自分としては満足でした。
TOEFL iBTのSpeakingは、あるトピックを英語で問われて、そのトピックに対して賛成か反対かを1分間で考えて英語で述べるのですが、この訓練は、のちのち留学時のプレゼンテーションの時に大いに役に立ったことを覚えています。英語は日本語と比較して論理的な言語ですので、論理的な構造で意見を述べる必要があります。そのため、日頃から日本語で結構ですので、論理的な意見を述べる訓練をしておくことをお勧めします。