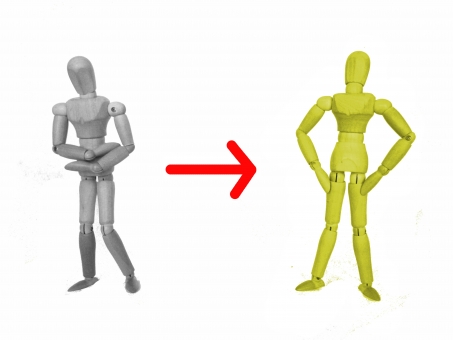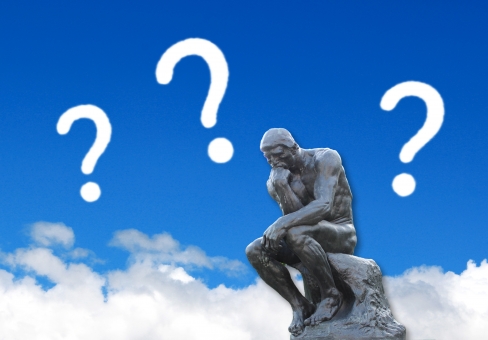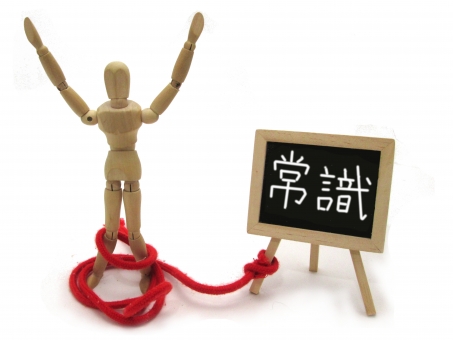周囲の人のモチベーションをあげさせる関わりの参考になる書籍を前回ご紹介しました。
この書籍は、元ラグビー日本代表監督を務められた平尾誠二さんの組織のリーダー論について表現されているものです。
この書籍の中で、平尾誠二さん自身の言葉で表現されているものをひとつずつ取り上げていきたいと思います。
「たとえ若輩者だろうと、きちんとリーダーシップを発揮してリーダーとしての務めを果たしているなら、ほかの選手はそのリーダーに敬意を払うし、リーダーの思い描くチームづくりに協力することを厭わない。これがいわば世界標準です。」
世界標準に到達したリーダーシップを発揮していきたいものです(自戒をこめて)。