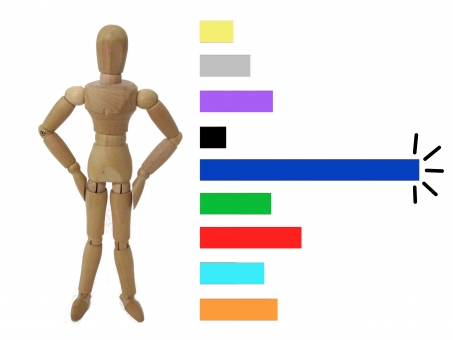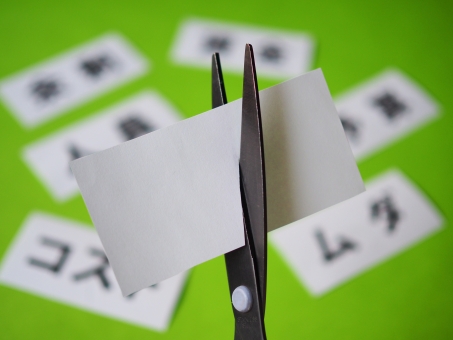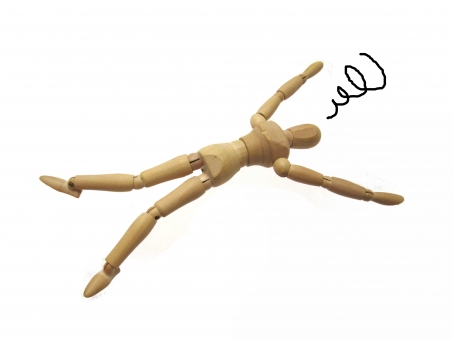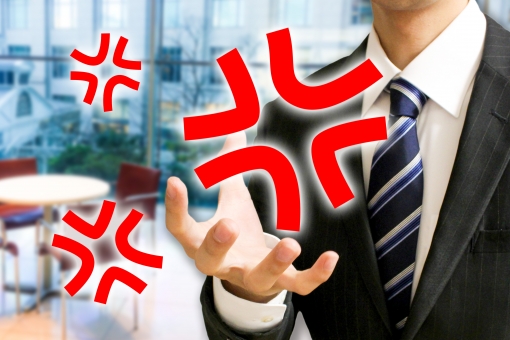周囲の人のモチベーションをあげさせる関わりの参考になる書籍を前回ご紹介しました。
この書籍は、元ラグビー日本代表監督を務められた平尾誠二さんの組織のリーダー論について表現されているものです。
この書籍の中で、平尾誠二さん自身の言葉で表現されているものをひとつずつ取り上げていきたいと思います。
「ぼく自身の経験からいっても、選手が思うように動かない、成長しないというときは、教える側の理屈や理論が原因というより、むしろ教えられる側の理解力や消化力に問題があるケースのほうが圧倒的に多い。
コーチングとは教える側の発信機ではなく、いかに教えられる側の受信機の精度を高めるかがポイントではないかと思うのです。
こちら側の受信機の性能を上げればいいのです。もう少し具体的に言いますと、まずは選手の話をよく聞くこと。この監督やコーチは自分の話をきちんと聞いてくれるとわかれば、選手のほうからいろいろと話してくれるようになります。」
とても示唆に富む考えですね。解釈など要らないですね。ぜひ、実践したいものです(自戒を込めて)。