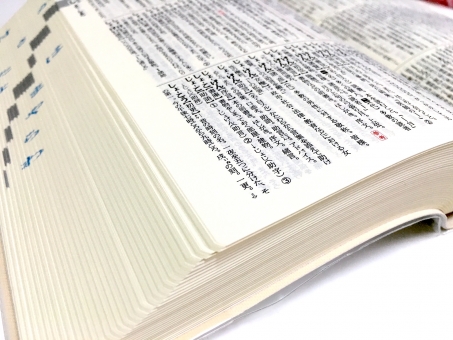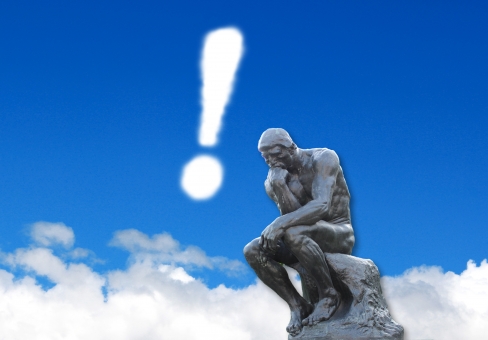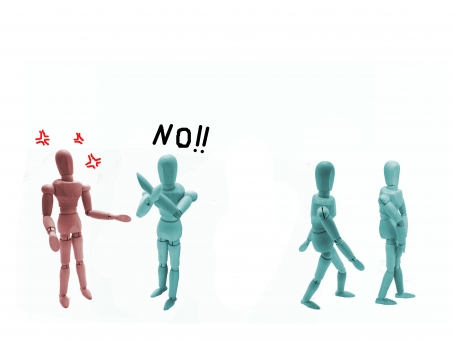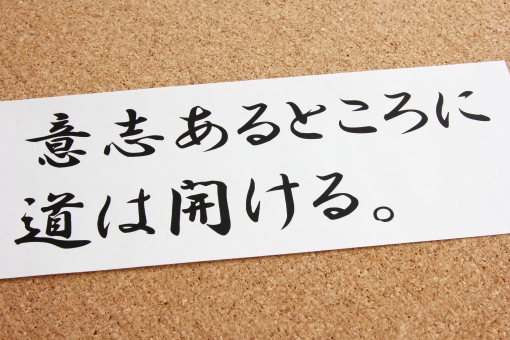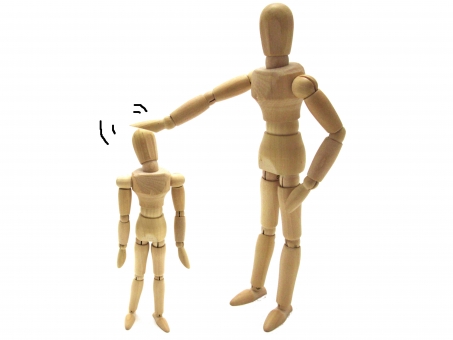周囲の人のモチベーションをあげさせる関わりの参考になる書籍を前回ご紹介しました。
この書籍は、元ラグビー日本代表監督を務められた平尾誠二さんの組織のリーダー論について表現されているものです。
この書籍の中で、平尾誠二さん自身の言葉で表現されているものをひとつずつ取り上げていきたいと思います。
「モチベーションをくじくようなことを、コーチは絶対やってはいけません。
たとえば、エースで四番をセカンドで二番にコンバートするとき、ピッチャーではアイツに勝てないからセカンドをやれという言い方。これはコーチとしては最悪です。
それは選手に妥協しろといっているのと同じではないですか。一度妥協した選手は、次に困難な状況に遭遇したときも、妥協することで解決をはかるようになるのです。目標値を下げればいいんだという思考回路になってしまう。そうなったらモチベーションはどんどん下がっていきます。」
選手・部下・学生などのモチベーションをあげて能力を引き出そうとする場合、上から目線で一方的に指導するやり方はよくないということですね。教育・指導の立場から、決めつけてかかってしまうと教育・指導の効果が上がらないこともうなずけます。このことは、学術的にも研究されており、学習効果があがらないことが証明されています(Hanushek EA, Woessmann L. Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries. The Economic Journal. 2006;116, C63–C76.)。では、学習効果をあげるにはどうすればよいかというと、学ぶ側に「選択させる」ことです。これも証明されています。ぜひ、実践していきたいと思います。