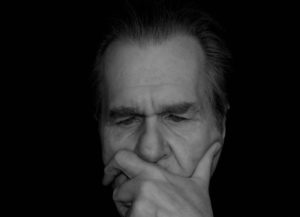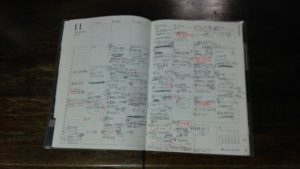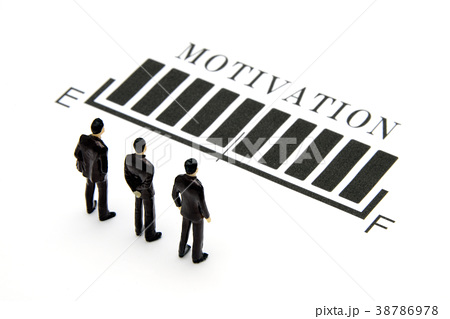英語で大学受験を失敗した私がアメリカ留学までできたまでの経緯を何回かにわたり書いてきました。
この一連の私の生き方で培ったもののなかで大きな部分をしめているのは、
「目標達成に必要なのことは、期限(期日)を設けて目標を決めることである。」
という考え方です。
期日を設けて達成したい目標に向かって実践行動を実直に実行することが大切です。
この過程を根底から支えるものがあります。それは、
「心」
です。「心」の充実の上に、個人のパフォーマンスや能力が発揮されて、目標達成に結びつきます。
その「心」を作っていく方法を一つずつご紹介していきます。

「心を使う」
まず、「心を使う」ことから始めます。
「心を使う」とは、シナリオ・ストーリー・未来を描き、イメージを鮮明にもつことを指します。
私の経験を基に「心を使う」を見ていきます。
大学病院を辞めて、正規留学の道を選択した時から「心を使う」を実践しています。
まずは、「TOEFL iBTのスコアを徐々に上げていき、2年以内にアメリカの医療系大学院の学籍を取り、留学を修了したのちはその経験を日本の現場(医療または教育)に活かす」というシナリオを描いていました。
このように留学の目的ははっきりしていましたので、イメージを鮮明に持っていたことになります。
心を使って、シナリオ・ストーリー・未来を描き、イメージを鮮明にもつと自然とモチベーションがあがります。
自分にとって価値ある目標を掲げたら、心を使って未来を描き、イメージを鮮明に持ちましょう。
次回も「心」に関するアプローチをご紹介します。

2020年2月12日更新