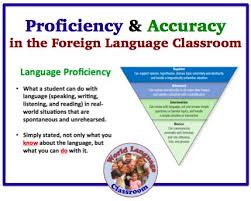昨日、「エビデンスのある教育を!」のところで述べましたが、習熟度別クラス編成について触れました。習熟度別クラスは、ピア・エフェクト(友人や周囲から受ける影響)の効果を高め、特定の学力層の子供たちだけでなく、全体の学力を押し上げるのに有効な政策であることが証明されています(Duflo E, Dupas P, Kremer M. Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. American Economic Review. 2011;101:1739–1774.)。ですが、習熟度別クラス編成の教育効果を上げるには、注意することがあります。
それは、習熟度別クラスの選択権を学生にゆだねる必要があるということです。
教員側が、例えば模擬試験の結果に基づいて、上位から3分の1を「発展クラス」、中位3分の1を「標準クラス」、そして下位3分の1を「基礎クラス」に割り当てると、教育効果が得られないことがメタアナリシスの検討から明らかとなっています(Kalaian SA, Kasim RM. Effectiveness of various innovative learning methods in health science classrooms: a meta-analysis. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2017;22(5):1151-1167.)。学生自身に自分の実力を自己評価させて、「今のレベルならば標準クラスから始めよう。」と、自分からクラスを選択することで、モチベーションが上がります。逆に、教員側から一方的に「あなたは基礎クラスからね。」と決められると学生のやる気をなくさせてしまうのです。
もう一つの注意点は、習熟度別クラスの教育期間です。1年のうち、4分の3以上の期間をあてて行うことが教育効果をあげるために必要であることが証明されています(「習熟度別少人数指導が学力に与える効果について ―鳥取県の小学校別データを用いた分析―」 政策研究大学院大学 教育政策プログラム 2014 年 2 月)。
つまり、1年間習熟度別クラスを編成して、定期的にテストを実施し、学生の理解度を確認しながら、習熟度別クラスを再編成していくのがよいと考えられます。