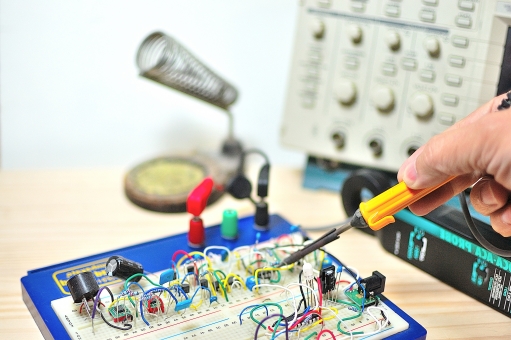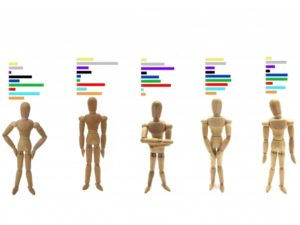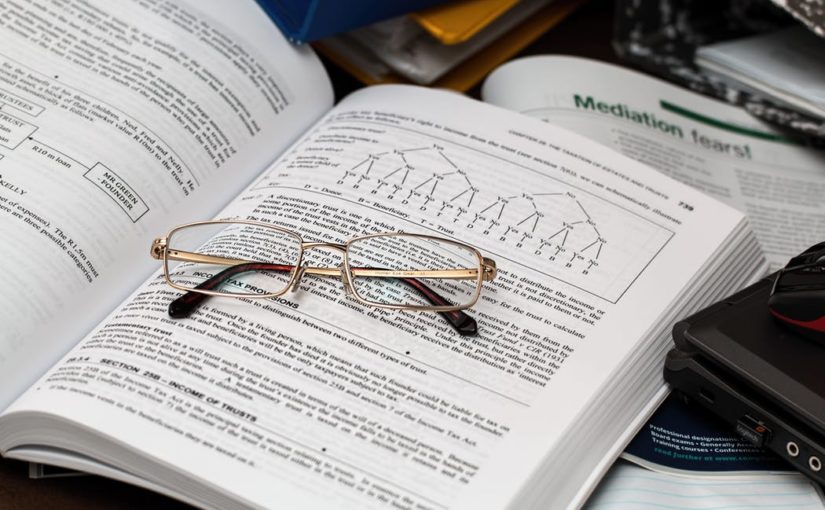このブログでは「モチベーションをあげる」ことをキーワードにしています。
を取り上げてきました。
このブログを見ていただいている皆さんの中には、社会人の方も多いと思います。
組織の大小にかかわらず、リーダーの位置で仕事をされている方も多いと思います。
世の中には立派なリーダーシップを発揮して組織をひっぱっている方々がたくさんいます。
その中でも、わたくしが人間的にも実績的にも尊敬できる人物に「ジーコ」さんがいます。
ジーコさんが書かれた著書に「ジーコのリーダー論」があります。
ジーコさんの実績に裏打ちされたリーダー論を紐解き、皆さんの組織のモチベーションをあげることに役立てていただけると幸いです。
「百人の部下がいれば、百通りの教え方がある」
「同じ組織内の人間同士がライバルとして競走し合い、たがいに結果を出していく。会社の中では、いちばんいい結果を出した人が、その部署でのお手本となる。そして、その結果、会社にとってもいい結果が出てくる。
しかし、リーダーとして気をつけなければならないのは、競争がライバルを邪魔したり、足の引っ張り合いにならないようにすることだ。部下に競争心を持たせることは、その組織にとって健康的なことだが、それはあくまでチームワークを軸にした競争でなければならない。もし、この軸が外れてしまうと、おたがいに相手を潰し合ったり、足を引っ張り合ったりして、結果的にチームに大きな打撃を与えてしまうことになる。リーダーは、このような不毛な事態に陥らないように、指導していく必要がある。」

私のおやじくらいの世代の人で言えば、プロ野球の野村克也選手と稲尾和久選手の関係でしょう。
私の世代の人で言えば、プロ野球の清原選手と桑田選手の関係でしょう。
最近の若い人の世代で言えば、サッカー日本代表の本田選手と香川選手の関係でしょう。
お互いに高め合い、実績を上げてこられた人ばかりです。
良いライバル関係は、良い相乗効果がこのように見られます。
一方、そうでない関係は、組織としても健全に発展していきません。
ジーコさんのおっしゃるように、リーダーは、組織を俯瞰して部下・選手・学生などを指導していく必要があります。
「チームワークを軸にした競争」
私も、このような環境を整えることが組織を発展させていくことであることを認識していきたいと思います。
「チームワークを軸にした競争」
「チームワークを軸にした競争」
「チームワークを軸にした競争」