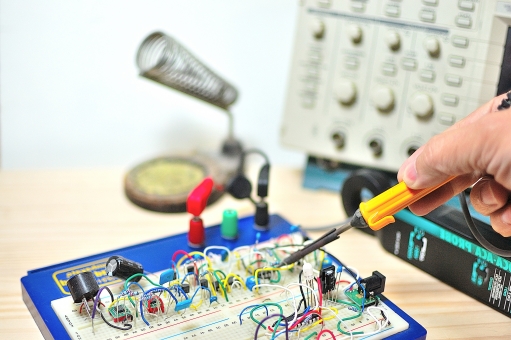このブログでは「モチベーションをあげる」ことをキーワードにしています。
を取り上げてきました。
このブログを見ていただいている皆さんの中には、社会人の方も多いと思います。
組織の大小にかかわらず、リーダーの位置で仕事をされている方も多いと思います。
世の中には立派なリーダーシップを発揮して組織をひっぱっている方々がたくさんいます。
その中でも、わたくしが人間的にも実績的にも尊敬できる人物に「ジーコ」さんがいます。
ジーコさんが書かれた著書に「ジーコのリーダー論」があります。
ジーコさんの実績に裏打ちされたリーダー論を紐解き、皆さんの組織のモチベーションをあげることに役立てていただけると幸いです。
「百人の部下がいれば、百通りの教え方がある」
「選手というものは、ひとりひとりそのキャパシティが違う。だから私は、そのキャパシティをオーバーするような役や責任を無理に渡そうとは思わない。その選手にできる範囲、できない範囲をよく見ておいて、それに応じた責任の分担を行っている。」

ジーコさんのおっしゃるように、ひとりひとりのキャパシティに応じた責任や役割を与えるには、リーダーは、ひとりひとりのキャパシティを推し量ることができるだけの日ごろのコミュニケーションが大切だということも言えると思います。
つまり、日ごろからの何気ない会話、あいさつ、表情の読み取りなどから情報をとり、部下・選手・学生などのひとりひとりのキャパシティを推し量っていくことですね。
ふと自分自身を振り返ると、一部の人に対してはできていないなと思いあたるところがあります。
対応できていると思える人とは、日ごろから決められた日誌を書いてもらい、定期的に私がポジティブな言葉を書き込んで返しているので、彼らのキャパシティを推し量ることは容易にできます。
でも、対応できていないなと思いあたる一部の人は、この日誌を書いてもらうことに同意を得られていません。
性格的に合わないようです。
ではどうすればコミュニケーションがうまくとれて、キャパシティを推し量ることができるか考えました。

「主体変容」の考え方です。
自分がまず変わり、他者を変えていく。
毎日30分、彼と話し合いをする時間を設けます。
テーマは、その時に浮かんだものにして、ざっくばらんに話します。
これを繰り返して、彼を「できる人」に導きたいと思います。