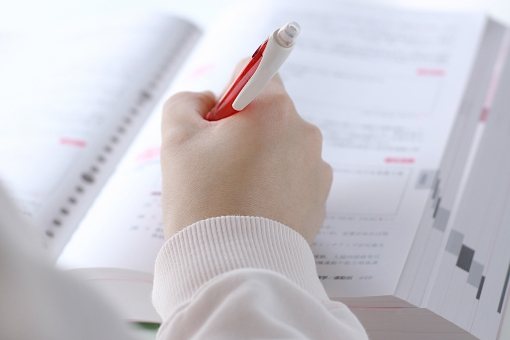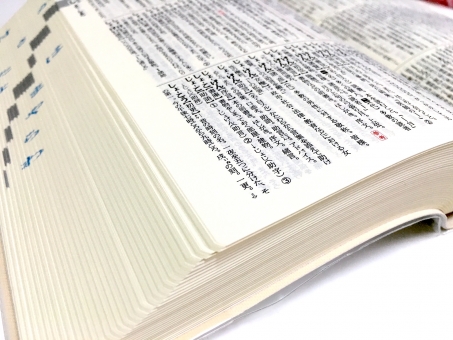周囲の人のモチベーションをあげさせる関わりの参考になる書籍を前回ご紹介しました。
この書籍は、元ラグビー日本代表監督を務められた平尾誠二さんの組織のリーダー論について表現されているものです。
この書籍の中で、平尾誠二さん自身の言葉で表現されているものをひとつずつ取り上げていきたいと思います。
「どの情報が必要で、どこが必要ではないかは、コーチが教えるというより本人が経験を重ね、そこから自分で学びとっていくものだと思います。ですから、強いチームで補欠に甘んじているより、実力にあったところでゲームに出たほうが絶対にいいのです。」
リーダーは、学生・選手・部下などに理論・理屈・方法などを教えたあとは、実践してもらうように関わり、経験を重ねる場を提供する役割があると解釈できます。「実力や理解力に応じた経験の場を与えること」とても参考になる視点ですね。ぜひ、教育者としてリーダーとして実践していきたいと思います。