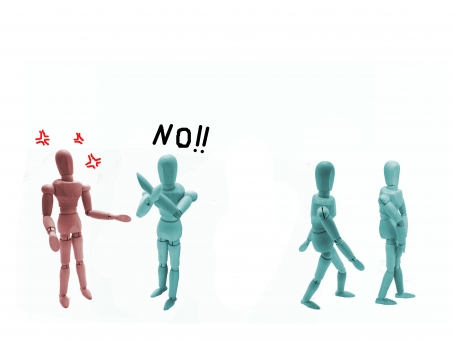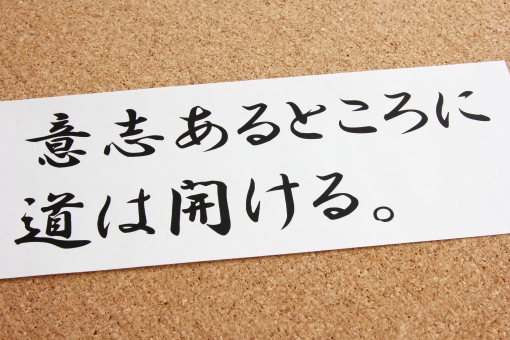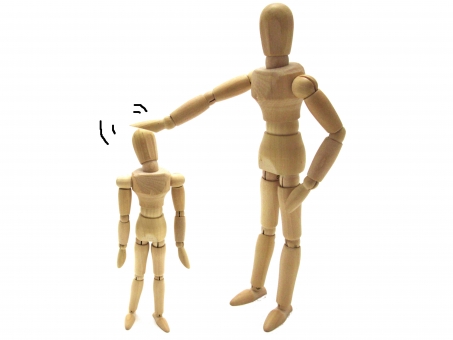周囲の人のモチベーションをあげさせる関わりの参考になる書籍を前回ご紹介しました。
この書籍は、元ラグビー日本代表監督を務められた平尾誠二さんの組織のリーダー論について表現されているものです。
この書籍の中で、平尾誠二さん自身の言葉で表現されているものをひとつずつ取り上げていきたいと思います。
「強い力で突き放すのは突き放すのが目的ではなくて、突き放した反作用でこちらに戻ってくることを期待しているのです。かつては、選手の反発係数が一様に高かったですから、そのやり方で非常に効果的でした。ところが、相手の反発係数が低くなると、このやり方は効率が悪い。
そこで、反発係数を高めるよりも、長所を見つけて褒めたり、おだててその気にさせたりすることで、こちら側に積極的に引き込むという方法が、現在では主流になりつつあるのです。」
従来の指導・教育は通用しない時代になったということをしっかり認識する必要性があることが読み取れます。指導者・リーダーの年齢が高ければ高いほど、この視点を持つ必要がありますし、意識して自分を変えていく必要があります。このブログでは”主体変容”というキーワードを時々取り上げてきましたが、まさに文字通り、「自ら変わり周囲を変えていく」ことが求められると言えますね。モチベーションを上げさせて人を育てるという観点からも参考になる視点だと思います。ぜひ、実践したいものです(自戒を込めて)。